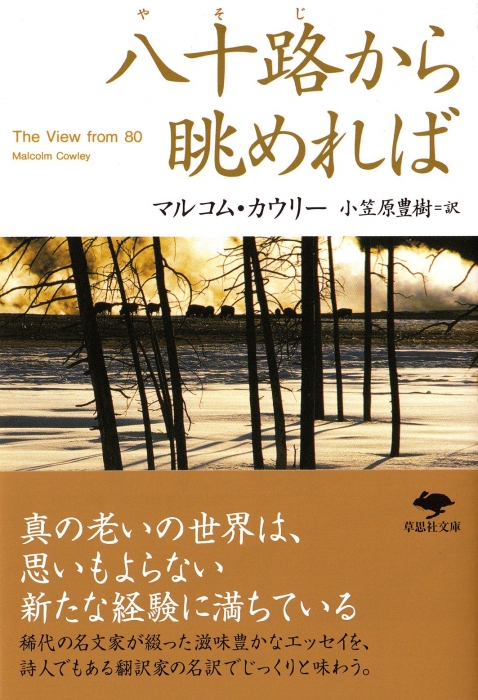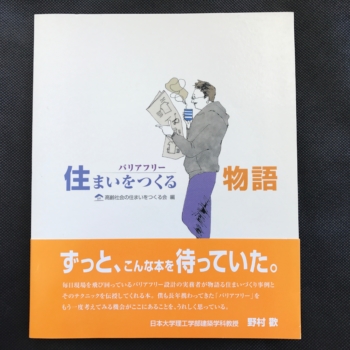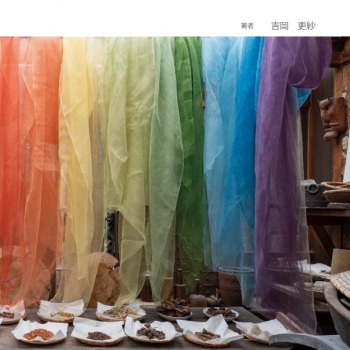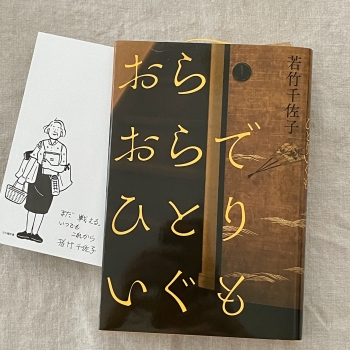以前紹介したボーヴォワールの『老い』は、文庫でも上下2巻という大作ですが、もう少し軽く「老い」についてのエッセイを読みたい方には、マルコム・カウリーの『八十路から眺めれば(The View From 80)』がおすすめです。いまは文庫版で出版されています。
マルコム・カウリーは、アメリカの文芸批評家、編集者、詩人。フィッツジェラルド、ヘミングウェイ、フォークナーといったロスト・ジェネレーションの作家たちと同世代の批評家として活躍したカウリーは、その後ヴァイキング・プレス社で出版人として半世紀にわたる活動を続けました。
本作は、80歳となったカウリーが、老いをテーマに書いたエッセイです。
老いを論じた筆者たちは、ざっと眺めた限りでは、その大部分が五十代終わり、あるいは六十代初めの「少年少女」たちである。少年少女は文学には詳しいかもしれないが、人生には必ずしも詳しくない。だから、せっせと統計を集め、医学の資料を漁る人がいるかと思えば、カメラやテープレコーダーをひっさげて老人を追い詰める人もいる。年老いた人間の気持というものが、こういう人たちにはわからないし、また、わかる筈もないのだ。(p.9-10)
そのまえがきで、カウリーは「50代・60代は、人生には必ずしも詳しくない」とバッサリと切り捨て、本書は1898年生まれの同年代の仲間たちへの「個人的なメッセージというかたちで、老年を共に生きる友人たちみんなの役に立つこと」を願う作品であると言っています。
文芸批評家としての豊富な知識を網羅して、軽妙なカウリーの筆は、ときにシニカルに笑いを誘いながら、八十歳から見える「老いの国」や「老いの技術」を紹介してくれます。キケロ、イエィツ、ヘミングウェイといった作家たちの例を縦横無尽に挙げつつ、それぞれのエピソードから見えてくるのは、80歳の視点から眺めた「真の老いの世界」のありようです。
またヴォーボワールが60歳のときに発表した『老い』については、「自分自身を含む万人の未来に関し、この人はペシミズムの荒涼たる気分のなかでむしろ浮かれているように見える」と評しています。確かに、ボーヴォワールの『老い』は、暗鬱たる雰囲気の中で、二十世紀に至る迄の膨大な老いの歴史を概観したものでした。これまで語られなかった老いの歴史をまとめ上げた点では価値のある作品ですが、カウリーの本作は、自分を含めた真の老人たちに対して「老後の計画」を持ち「大いに語れ」と鼓舞するものです。
詩人であれ主婦であれ、実業家であれ教師であれ、老人の一人びとりには、自分の正気を失いたくない限り、何らかの仕事の計画が不可欠だということである。(p.146-7)
七十歳を過ぎて絵描きになった銀行マン、七十八歳で油絵を描き始めたモーゼズお婆ちゃん、長く素寒貧な生活を送ったのち年老いてから投機を始めて八十三歳で死ぬまでに一財産を拵えた詩人、さまざまな人々の老後の計画の例は、興味深いものばかり。芸術家であれ、普通の人であれ、老いていつか旅立つまでの間の人生を慈しみ生きる大切さを、軽妙な筆運びで教えてくれるエッセイです。
著者:マルコム・カウリー(Malcolm Cowley)
翻訳:小笠原 豊樹
出版社:草思社
出版年:2015年